株式会社三菱地所設計についてですが、推定社員数は301~1000人になります。所在地は千代田区丸の内2丁目5番1号になり、近くの駅は二重橋前駅。株式会社Kipsが近くにあります。特許については2019年10月04日に『スクリーン装置』を出願しています。また、法人番号については「4010001081968」になります。 株式会社三菱地所設計の訪問時の会話キッカケ
株式会社三菱地所設計に行くときに、お時間があれば「相田みつを美術館」に立ち寄るのもいいかもしれません。
「
素晴らしい会社にお邪魔することができ、光栄に思います。
二重橋前駅の近くで美味しいレストランはありますか
相田みつを美術館が近くのようですが、どのくらい時間かかりますか
今、株式会社三菱地所設計の社員数はどのくらいですか
」
google map
JR東日本総武線の東京駅
JR東日本東海道本線の東京駅
東京メトロ丸ノ内線の東京駅
株式会社Kips
千代田区丸の内1丁目5番1号新丸の内ビルディング
株式会社スカイロボット
千代田区丸の内3丁目2番2号丸の内二重橋ビル2階
株式会社Novel
千代田区丸の内2丁目3番2号郵船ビルディング
2025年03月31月 16時
バス停SNSウェブアプリ《バスかめファン!》を公開
2025年01月23月 16時
エンターテインメントを通して考えるまちづくりの可能性
2024年06月28月 11時
《真に持続可能な社会》を実現するために 『ホワイトインフラ思考』にもとづ
2024年06月10月 19時
《空飛ぶクルマ》で変わる「これからのビル」とは?
2024年04月10月 13時
世界最大級の不動産見本市に初参加、当社のモビリティ×都市コンセプトを発表
株式会社三菱地所設計(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:谷澤 淳一)は、2025年3月11~14日にかけて、フランス・カンヌにて開催されたMIPIM 2025(不動産プロフェッショナル国際マーケット会議)に初参加し、「都市・建築・人をつなぎ合わせるツール」として、建物の内外を問わずに人の移動をシームレスなものとする新時代のモビリティ
『SMS:Seamless Mobility System』(以下、SMS)
に関する一連の構想を発表したことをお知らせいたします。
本リリースでは、その発表の概要をご紹介します。
MIPIM 2025にて発表する、三菱地所設計 デザインスタジオ 加藤 匠 シニアアーキテクト。
当社は、会場にて
『Seamless Mobility System』
と題したプレゼンテーションを実施しました。地上から空中にまで拡張する一連のモビリティの構想と、これにより変容する未来のまち・建築像を紹介。プレゼンテーション後には、海外のデベロッパーやメーカーからさまざまな質問や意見が寄せられ、活発なディスカッションが展開されました。建築設計事務所として、都市開発から個別の建築設計に至る、幅広い知見のもとでの提案力を有することを対外的に示しました。
MIPIM(Marche International des Professionnels de l’Immobilier)
は、1990年より毎年開催されている、投資家や不動産・建設企業、メーカー等が一堂に会する世界最大規模の不動産見本市。MIPIM 2025には90か国より2万人超の参加者が集いました。日本は、国土交通省と、民間企業・自治体14 団体による「ジャパンブース」を出展。カンファレンスや交流イベントを行いました。![]()
「未来のモビリティの仕組み」を通じて
「未来のまちの仕組み」「建築のすがた」を提案
当社が2023年度より継続して発表を行ってきた、
より自由な都市空間の利用を可能とするモビリティ構想『SMS』
は、路上を走行するキックボードや、ビル内外の境界を越えて移動できる小型モビリティ、これを空中にまで展開させたVTOL(垂直離着陸機。都市型の次世代航空交通として注目される「次世代エアモビリティ」「空飛ぶクルマ」)といった一連のモビリティに関する提案です。
人びとの移動の利便性を向上し、都市空間をより可変的で自由に使えるものにする『SMS』は、
建築設計事務所からのアプローチ
として、モビリティそのものの姿を描くだけでなく
「進化したモビリティによる『新たな移動』がインストールされた、未来のまち・建築のあり方」
の提案である点が特徴です。
2024年に発表したVTOLの構想をさらに拡張し、MIPIM 2025では(左図、左から)1人、2人、4人乗りのeVTOLモデルや、これにより姿を変える「未来のビル」(右図)を提案。※1人、2人乗りモデルは欧州における意匠権(欧州共同体意匠)を出願中。4人乗りモデルは、2024年に欧州共同体意匠 DM/235029、日本における意匠登録第1775924号を取得済。
可変的なシステムでシームレスな移動を可能とするモジュラー型VTOLシステム
当社が提案するVTOLは、プロペラ・キャビン・走行の3つのユニットから構成される、全自動操縦のモジュラー(組み合わせ)型のモビリティシステムです。
離発着ポートと一体で機能し(後述)、ポートからポートへの空中移動に限らず、空中と地上への移動をもシームレスにつなぎ合わせます。
2人乗りのVTOL。モジュール(ユニット)の組み合わせで飛行モードと走行モードに変形。![]()
映像配信中/空中と地上の移動をつなぎあわせる「進化した未来のビル」の姿とは
MIPIM 2025では、こうした空中・地上を移動するモビリティよって姿を変える建築と都市の姿を描き出した『SMS』のコンセプトムービーを上映、高い好評をいただきました。
本ムービーをWebにて配信中(https://vimeo.com/1061124625)です。
下記リンクよりご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=yPr5yFIyKNY
【MIPIM2025】Seamless Mobility System / Mitsubishi Jisho Design Inc.![]()
『SMS:Seamless Mobility System』
コンセプトムービーの一部をご紹介します
VTOLにより、ビルの「新たな玄関」となる屋上の姿。離発着ポートとして、旅客や荷物の乗降や、VTOLとPodbusのモード転換などが行われます。パーゴラ屋根にはプロペラユニットを懸架しておくことができます。
空中輸送のために、屋上付近に荷捌きを設置。これにより1階部分の荷捌きや倉庫といったスペースを縮小。よりオープンな都市空間を実現します。
Podbusを移動させる垂直動線がビルの新たな機能に加わります。従来のエレベータと異なり、1つのリフト(レーン)に複数のパレット(床板)を稼働させることで待ち時間を短縮するシステムを構想。エレベータもまたモビリティのひとつとして、「シームレスであること」を追求しました。
モビリティのビルへの導入によって大きくその構成を変えるオフィスフロアも紹介。地上や上空から各階へと直接アクセスできるようになり、小型搬送ロボットやキックボードのポートが共存する「モビリティハブ空間」が出現。ワーカーの働き方・オフィスでの過ごし方の変化にもつながります。
VTOLの離発着ポートが屋上や中間階に設けられるほか、モビリティの出入りを可能とするより自由度の高い1階などにより新たな姿へ進化した「未来のビル」とそれにより構成される都市の姿を描き出しました。![]()
『SMS:Seamless Mobility System』関連リリースのご紹介
MIPIMでの発表に先立ち、2024年4月に当社のVTOL構想の第一弾となるニュースリリースを配信いたしました。詳細については下記リンクよりリリースをご覧ください。
《空飛ぶクルマ》で変わる「これからのビル」とは?
都市×建築×次世代エアモビリティからなる一連の運用システムとデザインを提案
https://www.mjd.co.jp/news/55625/
(発表:2024年4月10日)![]()
三菱地所設計の海外訴求力強化に向けた取り組み
当社は、現地法人(上海、シンガポール)を構える東・東南アジア地域を基盤として、より一層の海外マーケットの拡張に向けた対外的な訴求力の強化に取り組んでいます。このたびのMIPIMへの出展は、当社が未来を見据えた建築・都市のビジョンを描き、技術的イノベーションを取り入れた都市マスタープランや建築提案を可能とする組織であり、三菱地所グループの一員としての高い機動力を有することを広く発信する取り組みの一環です。![]()
『SMS:Seamless Mobility System』ブックレットを販売中です
公共交通の利用活性化でまちづくり / 公共交通オープンデータチャレンジ2024に参加中
このたび、
株式会社三菱地所設計
(東京都千代田区、代表取締役社長:谷澤 淳一、以下 三菱地所設計)と
Pacific Spatial Solutions株式会社
(東京都千代田区、代表取締役:八十島 裕、以下PSS)は、香川県丸亀市におけるコミュニティバスやデマンド型交通(※1)の利用促進や周辺地域の活性化を目指し、バス停SNSウェブアプリ
《バスかめファン!》
の試験運用を開始したことをお知らせいたします。
《バスかめファン!》
は、公共交通オープンデータ協議会、国土交通省の主催による「公共交通オープンデータチャレンジ2024」(※2)の応募作品です。
バスSNSウェブアプリ《バスかめファン!》
「『かめ丸』を育てて、まちのファンになる」バス停に関する新たな情報プラットフォーム
バスを楽しみ(fun)、丸亀のファン(fan)の輪を広げる
《バスかめファン!》
は、丸亀市内のバス停についての要望や周辺スポットのシェアしたい情報を投稿したり「いいね」することで、各バス停に住むキャラクター「かめ丸」をみんなで育てる、ゲーム要素を持ったウェブアプリです。
《バスかめファン!》
は、各バス停の位置と時刻表を表示するだけでなく、その周辺エリアに関する声を収集するなど、利便性の高い機能を備えています。これにより、地域住民・交通事業者・行政・観光客などの多様なステークホルダーをつなぐプラットフォームとなり、バスや地域の魅力を発掘します。公共交通の利用を促進することで地域の活性化を図る、新たなまちづくりの取り組みの一環です。
公共交通の利用促進から、地域の活性化につなげる試み
長年にわたって国内外の各地でまちづくりに参画してきた三菱地所設計は、2024年10月、衛星リモートセンシング技術で得られるデータを活用した「
容積充足率マップ
」(※3)を公開するなど、『まちづくりDX事業』としてデジタル技術を駆使した新たなまちづくり手法の確立に取り組んでいます。
このたび、三菱地所設計と、地理空間データの解析やデジタルツイン技術を活用した課題解決を図るPSSの2社は、「まちづくり」と「交通」という観点から、「地方都市における公共交通の利用者の減少」に共通の問題意識を持ち、より多くの人に公共交通を利用してもらい、それによって周辺エリアの活性化を図る取り組みの第一歩として、
《バスかめファン!》
を開発しました。
誰もが親しみやすいサービスの提供を目指すとともに、開発に際してはバス運営事業者や市行政へのヒアリングを実施し、さまざまなニーズの反映を行っています。
《バスかめファン!》画面イメージ。地図上にプロットされたバス停・バス路線の参照のほか、ユーザによる各バス停への情報の投稿などにより加算されるポイントに応じ、「かめ丸』を育てます。
バス停のキャラクター「かめ丸」。ポイントに応じて卵から成長します。
お気に入りのバス停や周辺スポット、観光資源の『良かった』情報を投稿したり、「いいね」することで、情報を広く共有しコミュニティの強化を図ります。また、多くの人に周知したいことを『お知らせ』することや、『リクエスト』として、施設整備や修繕の要望を投稿することもでき、これらの声を交通事業者が収集したり、行政の交通政策へ活用することも可能となります。
バス利用を伴う生活や観光の活性化を図るにあたり、みんなでバス停に住む「かめ丸」を育てるゲーム要素を持ったアプリとすることで、こどもから大人まで楽しく利用でき、バス利用者のすそ野拡大やバス停および周辺のまちへの愛着の向上を図ります。
丸亀市を走るコミュニティバス
丸亀市の観光資源・周辺スポットの例。新日本百名山のひとつ飯野山(讃岐富士)
丸亀市の観光資源・周辺スポットの例。金毘羅詣でのシンボル「太助灯籠」![]()

《バスかめファン!》
は、
「公共交通オープンデータチャレンジ2024」の開催期間(2025年3月14日までを予定)に合わせて試験運用を行います。
期間中はどなたでもご利用可能です。下記URLまたは二次元コードよりご利用ください。
https://buskame.jp/
(最新の開催情報は、
「公共交通オープンデータチャレンジ2024」公式Webサイト
をご覧ください)![]()
試験運用終了後の本格的な運用については、今後の検討を経て方針を決定いたします。三菱地所設計とPSSは今後も多様な観点からまちづくりに関する取り組みを進めてまいります。
※1 デマンド型交通とは、利用者の予約に応じて経路やスケジュールを定め、運行される地域公共交通のこと。
※2「公共交通オープンデータチャレンジ2024」(
https://challenge2024.odpt.org/
)は、各種の国内公共交通オープンデータ等を活用し、社会課題の解決や地方創生に資する新たなアプリケーションサービスを募集するもの(実施期間:2024年7月16日~25年3月14日)。本アプリの開発に際しては、丸亀市でコミュニティバス事業を展開する琴参バスの運行データ(一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会が公開)と、デマンド交通事業を展開する琴平バスの運行データ(同社より提供)を使用。
※3「
容積充足率マップ
」は三菱地所設計と一般財団法人リモート・センシング技術センターの共同開発による。![]()
関係者プロフィール
三菱地所設計は、1890(明治23)年の創業以来、東京都千代田区丸の内に拠点を構え、都市計画から建築設計・監理、企画・コンサルティング、リノベーション、コンストラクションマネジメントなど、広がり続ける活動領域に130年を超える技術の蓄積やネットワークで向き合う、日本で最も歴史ある組織設計事務所です。中国・上海とシンガポールに海外拠点を設け、東アジア・東南アジア全般に展開。日々多様な業務に取り組んでいます。
https://www.mjd.co.jp/
Pacific Spatial Solutions株式会社は、地理空間データを活用して、お客様の課題解決を行う企業です。GIS(地理情報システム)、地理空間データパイプライン構築、大規模空間データ解析、デジタルツインソリューションなど、世界最先端の2D/3D地理空間技術を用いた様々なソリューションを提供します。
https://pacificspatial.com/
当イベントは、3Dホログラム界の先駆者として知られるKAZU氏と、世界最高峰の舞台で活躍するダンスアーティスト、KENTO MORI氏を招き、二方のコラボレーションによるARパフォーマンスと、社員からの質問に答える対談形式のトークセッションを行ったものです。
当社は2020年8月に、スマートフォンを用いて手軽にホログラムを体感することのできるツール「SMAHOLODEO(スマホロデオ)」(https://www.mjd.co.jp/rd/works/works15.html)を発表いたしました。当イベントは、その開発を行った当社R&D推進部に所属するエンジニアが開発過程でKAZU氏と出会ったことを契機とし、最新の技術を取り込んで表現の幅をより一層拡張しているエンターテインメントの世界に触れることを目的に開催したものです。

▲動きに合わせて、その場でARエフェクトが生成されるダンスパフォーマンス。
パフォーマンスを体感し、これからの建築・都市デザインへと展開し得る新たな視点を獲得できたと同時に、「スマホロデオ」をはじめとするホログラムやAR/VRといったビジュアライズ手法、日々進化を遂げるエンターテインメントとの融合が、私たちが手がけるプロジェクトや今後のまちづくりをどのように変え得るものか、といった示唆に富んだイベントとなりました。
■ 最新技術を駆使したダイナミックなパフォーマンスを披露
本イベントの前半では、普段は打ち合わせや催事に使用されている、三菱地所設計本店 スタジオを舞台に、 KENTO MORI 氏の全身に取り付けたセンサをもとに、空間の奥行や身体の特定の動作を感知しその場でARエフェクトを生成する「リアルタイムモーションキャプチャー」で、ダイナミックに展開されるAR演出を用いた AR ダンスライブを開催。世界の名だたるトップアーティストから必要とされる一流のダンスパフォーマンスを披露いただきました。
後半では、当社社員から募った質問をもとに、KAZU 氏と KENTO MORI 氏が対談形式でトークセッションを展開。「誰もがわくわくできるまち」づくりの可能性や、多様な人びとの表現を受容し、育てる場となる寛容な建築への展望が語られ、真に豊かな社会の創造に向け、さまざまな視点を持つプレイヤーが領域を超えて協働していくことの重要性を改めて認識するものとなりました。

▲上2点・下左:オフィス内に当社社員が設営したステージでパフォーマンスを行う KENTO MORI 氏。その場で瞬時にモーションデータを取り込む「リアルタイムモーションキャプチャー」を用いている。 ▲右下:対談形式のトークセッション(ステージに向かって左:KENTO MORI氏、同右:KAZU氏)。
今回、オフィス内に当社社員が仮設した簡易的なステージに、KENTO MORI氏が所属するKM1とMOMENT FACTORY(カナダ発の世界最高峰デジタルアート集団)が共同開発したARキットを持ち込み、高精度のARパフォーマンスを行い、空間の質やその規模の制約を受けずにハイクオリティな演出が可能であることを実証。建築空間と、最新の技術を用いた表現手法、これを用いたエンターテインメントの融合において、既知のあり方を超えた提案への糸口を掴むことができました。
こうしたイベントなどを介して、当社はより幅広い視点から建築・都市のありかたを探求し、豊かな建築設計やまちづくりの可能性を探り続けてまいります。
■ コラボレーションパフォーマンスを披露いただいた登壇者紹介
▼KAZU(カズ)
2016年に当時世界初となる最新3Dホログラム技術を発信して以降、常に最先端の演出力を追求しているホログラマー。完全なメイド・イン・ジャパンブランドで、ホログラム界の先駆者として、同技術の先進国であるイギリスやアメリカに劣らないエンターテインメントを提供しています。「Creator is King」の精神で未来を明るくし、人びとの日常に“わくわく”を届ける最新技術を駆使した演出で、日本から世界へ発信し続けています。
▼KENTO MORI(ケント・モリ)
マイケル・ジャクソンやマドンナをはじめ、世界が認めるダンスアーティスト。21歳で渡米し、プロダンサーとしてマドンナ、クリス・ブラウン、アッシャーなどの専属ダンサーを務め、グラミー賞をはじめとするアワードショーにも出演。アメリカを拠点に、50 カ国 200 都市以上でパフォーマンスを行っています。2016 年以降は、音楽と最先端 AR 技術を融合させた新しい表現を取り入れたパフォーマンスで、世界中の観客を魅了しています。近年では日本各地のさまざまな自治体と連携し、地域に根付く伝統文化と舞の表現を掛け合わせ、さまざまなSHOWコンテンツを創造し魅力を発信する「#日本を世界へ」プロジェクトを展開しています。
■ スマホの情報を宙に浮かせる机上ツール、「SMAHOLODEO(スマホロデオ)」(R)(https://www.mjd.co.jp/rd/works/works15.html)
現実とヴァーチャルを融合させるMR(Mixed Reality)技術の可能性は建築設計分野でも広がりを見せています。目の前にヴァーチャルな建築を出現させ、見えない熱や空気を可視化し、インタラクティブに扱うことができます。この技術は、立体的で直感的なイメージ共有を可能にするコミュニケーションツールとしても注目されています。
三菱地所設計では、2020年よりR&D推進部にてMRを身近に扱える簡易ツール開発をスタート。その第1弾が「SMAHOLODEO(スマホロデオ)」です。スマートフォンの表示情報を宙に浮かせる机上ツールで、フィギュアやCGが立体的に浮かび上がり、パフォーマンスやメッセージを伝えます。紙製で簡単に組み立てられ、持ち運びも容易。映像コンテンツに合わせて自由にデザインでき、プレゼンテーションやノベルティとしても活用可能です。([特許登録]特許第6656460号/[意匠登録]意匠第1664201号)


▲スマホロデオ。製品本体は紙製で、ユーザーが折って簡単に組み立てられる仕様。スマホのホールド角度、スクリーンの角度などの最適解を求め、組み立てはシンプルに、材料の無駄が少ない構成を検討した。
■ 三菱地所設計のR&D推進部について
R&D推進部は、エンジニア(技術者)のみならず、アーキテクト(建築設計者)やプランナー(都市計画家)といったさまざまな職能者が所属する、全社にまたがる領域横断型の部署です。
「テクノロジーと生活を結び、豊かな空間づくりを実現する」ことを目指し、各分野の第一線で活躍するプレイヤーとつながり、木造・木質化の推進や、スマートシティの研究提案をはじめとする広範なテーマに取り組んでいます。当部の取り組みについて、詳しくはWebサイト(https://www.mjd.co.jp/rd/)をご覧ください。
===

三菱地所設計は、1890年の創業以来、東京都千代田区丸の内に拠点を構え、都市計画から建築設計・監理、企画・コンサルティング、リノベーション、コンストラクションマネジメントなど、拡張する活動領域に130年を超える技術の蓄積やネットワークで向き合う、日本で最も歴史ある組織設計事務所です。今日、国内のみならず、中国・上海とシンガポールに海外拠点を設け、東アジア・東南アジア全般に展開し、日々多様な業務に取り組んでいます。
『ホワイトインフラ思考』は、「空間に冗長性・柔軟性・可変性を与え、さらにそれが持続する仕組みを構築するための考え方」です。
この考え方に基づいて、ハードとソフト、スケールの大小を超えた取り組みを図ることで、今日多様さを増しつつある当社の活動を、従来の設計事務所の枠に収まることなく、さらに幅広いものとして展開させていくことができます。私たちは、多種多様なアプローチにより急速かつ複雑化を遂げるさまざまな社会課題を解決し、《真に持続可能な社会》を“Design”してまいります。

▲ 社会課題・時代の変化へ対応できる、《真に持続可能な社会》の実現に取り組むための3つの要素。特に「冗長性を持った、柔軟で可変する空間」をハードとソフトの両面から構築し機能させる考え方が『ホワイトインフラ思考』です。
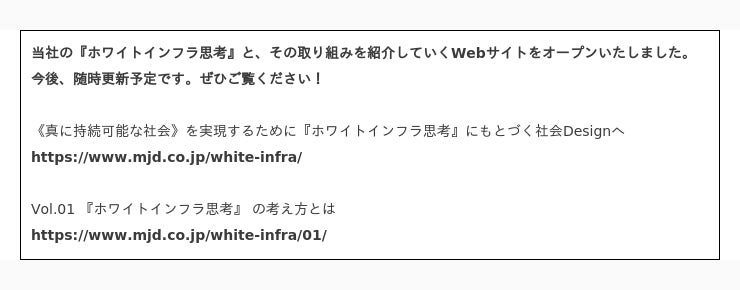
ホワイトインフラ思考』Webサイトの掲載コンテンツについて
『ホワイトインフラ思考』の実践アプローチ
130年以上の歴史を持つ当社では、まちの継続的成長やそこで過ごす人びとの営みへの視座に、「持続可能性への取り組み」と位置付けられる思想が継承されてきました。
《真に持続可能な社会》の実現に向けて、これらを《ソフト的可変性》《ハード的可変性》《最先端技術の活用》の3つを軸とした『ホワイトインフラ思考』のアプローチへと整理しました。多様なプロジェクトでの実践を図ってまいります。

▲ 『ホワイトインフラ思考』の実践アプローチ。
このアプローチにより、プロジェクトの初動期から、運用を経て、さらなる改善を考えるアフター期まで、さまざまなフェーズで柔軟性や可変性を都市や建築に組み込むことができます。社会全体のフレキシビリティを向上させる取り組みのサイクルです。
『ホワイトインフラ思考』に基づく、三菱地所設計の “Design” 事例
現代が抱える多様な社会課題の解決に取り組んだ、『ホワイトインフラ思考』の実践を、さまざまなプロジェクトを事例に紹介してまいります。今後、定期的にアップデートしていく予定です。

▲ 上図では、「3rd MINAMI AOYAMA」(2023年竣工)を事例に、社会課題(左上)に対して、さまざまな計画のフェーズで、どのような「ホワイトインフラ思考」のアプローチを図っていったかを示しています。

三菱地所設計(Mitsubishi Jisho Design Inc.)は、1890年の創業以来、東京都千代田区丸の内に拠点を構え、都市計画から建築設計・監理、企画・コンサルティング、リノベーション、コンストラクションマネジメントなど、拡張する活動領域に130年を超える技術の蓄積やネットワークで向き合う、日本で最も歴史ある組織設計事務所です。今日、国内のみならず、中国・上海とシンガポールに海外拠点を設け、東アジア・東南アジア全般に展開し、日々多様な業務に取り組んでいます。
このたび、『SMS』のアイデアを都市の上空にまで展開し、より自由な空間利用を可能とするeVTOL※ のあり方を新たに提案することをお知らせいたします。
※ eVTOL:電動垂直離着陸機。都市型の次世代航空交通として注目される乗り物(次世代エアモビリティ、空飛ぶクルマ)。

△『SMS:Seamless Mobility System』の延長・発展としてデザインしたeVTOLである「Passenger VTOL」。3つのユニットの合体・分離で空・陸のシームレスな移動を実現します。
■「未来のモビリティの仕組み」から「未来のまちの仕組み」「建築のすがた」の提案へ
本提案では、建築設計事務所からのアプローチとしてeVTOLそのものの姿を描くだけでなく、「進化したモビリティがインストールされた未来のまちのあり方」を追求しています。
『SMS:Seamless Mobility System』として提唱した新しい移動のあり方をさらに発展させるものとして、都市における移動の利便性を一層向上させ、都市空間を、より可変的で、自由に使えるものにしていくための構想であるとともに、ここで提案するeVTOLを介して、人やモノがビルの屋上や中間階に直にアクセスできるようになることで、ビルという建物のタイポロジー(建築の型)に大きな変革をもたらします。
一連の構想を現代の都市・建築の多様な課題に応える当社の提案に導入・展開してまいります。
■可変的なシステムでシームレスな移動を可能とするモビリティ「Passenger VTOL」

当社が提案するeVTOL「Passenger VTOL」は、プロペラ・キャビン・走行の3つのユニットから構成される、4人乗りの全自動操縦型電動式のモジュラー型モビリティシステムです。バーティポート※(後述)と一体的に機能し、ポートからポートの空中だけでなく、空中と地上の「間」の移動をも、シームレスにつなぎ合わせます。こうしたデザインの独自性が認められ、このたび欧州における意匠権(欧州共同体意匠DM/235029)を取得いたしました。
※ バーティポ―ト(Vertiport)は「垂直離着陸用飛行場」を指す、垂直(Vertical)+空港(Airport)からなる言葉。

△ 各ユニット・パーツが着脱できる、3Dプリンタを用いたモデル作成(縮尺1/12)を行ってデザインの検証を行っています。
■新たなモビリティにより変化し、空中と地上の移動をつなぎあわせる「ビル」の姿とは
eVTOLの登場で、従来までの地上のエントランスに加え、「新たな玄関」となるのがビルの屋上や中間階です。ここは「Passenger VTOL」の離発着のためのバーティポートとなり、旅客乗降、荷物の積み下ろし、「Passenger VTOL」のモード転換などが行われます。ビル外壁面には、人を乗せたままで「Passenger VTOL」を地上との間で昇降させる機構が設けられます。
これによって、都市における新たな物流・人流の拠点としての役割を、ビルに与えることができます。

バーティポートが設けられたビルのイメージ。
1. 上空を飛行する「Passenger VTOL」。
2. シームレスな離発着を可能とする、プロペラユニットを装着するパーゴラ屋根。
3. プロペラユニットを切り離し、屋上を移動する走行モードの「Passenger VTOL」。
4. 新たなビルのエントランスとなった屋上階には、ロビーをはじめとする利用者待合スペースとしての機能が設けられます。
5. 屋上と地上との間で、エレベータのゴンドラのように「Passenger VTOL」を昇降させる搬送システム。各階への着床も可能な、外壁部に設けられる新たなビルの建築要素。
6. 地上に降りた「Passenger VTOL」は、そのまま都市内を移動していきます。
■新たな人とモノの流れを生み出すバーティポート

1. パーゴラ屋根。フレーム内のガラス面では高効率の太陽光発電を行うことも想定。懸架された「Passenger VTOL」プロペラユニットが充電されています。
2. エレベータでせり上げられたキャビンユニットは、プロペラユニットと合体し、飛行モードへと切り替わります。
3. 充電中の走行ユニット。バーティポートに到着した飛行モードの「Passenger VTOL」は、走行ユニット上に着陸・ドッキングし、自走できるようになります。
4. 「Passenger VTOL」は、物流の仕組みとして展開させることも可能。さまざまなモビリティを組み合わせた一連のシステムで、ビルは都市の新たな物流の拠点となります。
■「新たな都市のあり方」の提案への展開:三菱地所のコンセプトムービーに登場
本提案における「Passenger VTOL」とバーティポートの一連の構想は、
2024年2月13日に三菱地所株式会社より発信されたリリース『空飛ぶクルマの社会実装に向け、都心でのヘリコプター運航実証を開始』(https://www.mec.co.jp/news/detail/2024/02/13_mec240213_sorakuru)と、そのコンセプトムービー(https://youtu.be/RGMZKzB-eKE)などに登場しています。合わせてご覧ください。

△三菱地所プレスリリース上での提案の展開。
■補足情報:ブックレット『SMS:Seamless Mobility System』について

建築や都市の設計に携わる当社のアーキテクトらによる、さまざまなモビリティが都市・建築・人びとの過ごし方をどう変えるか、という社会提案をまとめたブックレット『SMS:Seamless Mobility System』を販売中です。
掲載中の複数のモビリティで意匠権を取得しており、今後、実機の開発や、都市・建築の提案への導入を図ってまいります。
ブックレット『SMS』(A4変形版、全92頁、定価:3,000円+税)のお買い求めや、内容のご説明等に関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
▶三菱地所設計Webサイト お問い合わせフォーム https://www.mjd.co.jp/contact/
■補足情報:関連リリースのご案内

上記ブックレットを紹介したプレスリリース(発信:2023年8月4日)では、それぞれのモビリティのコンセプトの詳細な説明のほか、電動キックボードのプロトタイプ「Scooter PM01 Prototype」の紹介を行っています。(https://www.mjd.co.jp/files/news_detail/file/864/file.pdf)
また、本コンセプトをまとめたムービーを、YouTubeにて公開(2024年3月5日)しています。合わせてご覧ください!

三菱地所設計 デザインスタジオ
三菱地所設計にて、『SMS』をはじめ次世代のモビリティの検討を進めるデザインスタジオは、産業構造の変化や価値観の多様化といった今日の社会変化の中、将来を見据えた戦略策定に取り組むべく「社内のさまざまな知見を横断的に束ね」「組織設計事務所の総合力として発揮する」部署です。
社会環境のリサーチや分析から、創造的かつ価値を最大化するソリューションを提案。多様なサービスを通じ、都市規模から改修・インテリアまで、現代の多様なニーズに応えています。

三菱地所設計(Mitsubshi Jisho Design Inc.)
三菱地所設計は、1890年の創業以来、東京都千代田区丸の内に拠点を構え、都市計画から建築設計・監理、企画・コンサルティング、リノベーション、コンストラクションマネジメントなど、広がり続ける活動領域に130年を超える技術の蓄積やネットワークで向き合う、日本で最も歴史ある組織設計事務所です。中国・上海とシンガポールに海外拠点を設け、東アジア・東南アジア全般に展開。日々多様な業務に取り組んでいます。
株式会社三菱地所設計の情報
東京都千代田区丸の内2丁目5番1号
法人名フリガナ
ミツビシジショセッケイ
住所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番1号
推定社員数
301~1000人
周辺のお天気
周辺の駅
4駅東京メトロ千代田線の二重橋前駅
地域の企業
3社
地域の観光施設
特許
2019年10月04日に『スクリーン装置』を出願
2018年09月04日に『制震構造物』を出願
2016年03月24日に『照明システム』を出願
2014年05月28日に『循環システム』を出願
法人番号
4010001081968
法人処理区分
新規
プレスリリース
【コンセプトムービー公開中!】《空飛ぶクルマ》で変わる「これからのビル」
【コンセプトムービー公開中!】《空飛ぶクルマ》で変わる「これからのビル」とは?
2025年03月31月 16時
【コンセプトムービー公開中!】《空飛ぶクルマ》で変わる「これからのビル」とは?
バス停SNSウェブアプリ《バスかめファン!》を公開
2025年01月23月 16時
バス停SNSウェブアプリ《バスかめファン!》を公開
エンターテインメントを通して考えるまちづくりの可能性
2024年06月28月 11時
一流アーティストを招いた社内イベントを開催しました株式会社三菱地所設計(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:谷澤 淳一)は、去る5月、未来のまちづくりを考える社内イベント「世界を知る者が考える、エンターテインメントと日本のまち」を開催いたしました。
《真に持続可能な社会》を実現するために 『ホワイトインフラ思考』にもとづく社会Designへ
2024年06月10月 19時
その考え方・取り組みを紹介するWebサイトをオープンしました株式会社三菱地所設計(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:谷澤 淳一)は、さまざまな変化や多様性を受け入れ、進化し続けることのできる《真に持続可能な社会》をつくっていくための考え方として、新たに『ホワイトインフラ思考』を提案することをお知らせいたします。
《空飛ぶクルマ》で変わる「これからのビル」とは?
2024年04月10月 13時
都市×建築×次世代エアモビリティからなる一連の運用システムとデザインを提案株式会社三菱地所設計(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:谷澤 淳一)は、「都市・建築・人をつなぎ合わせるツール」として、建物の内外を問わずに人の移動をシームレスなものとする、新時代のモビリティ『SMS:Seamless Mobility System』の構想を提唱してまいりました。
