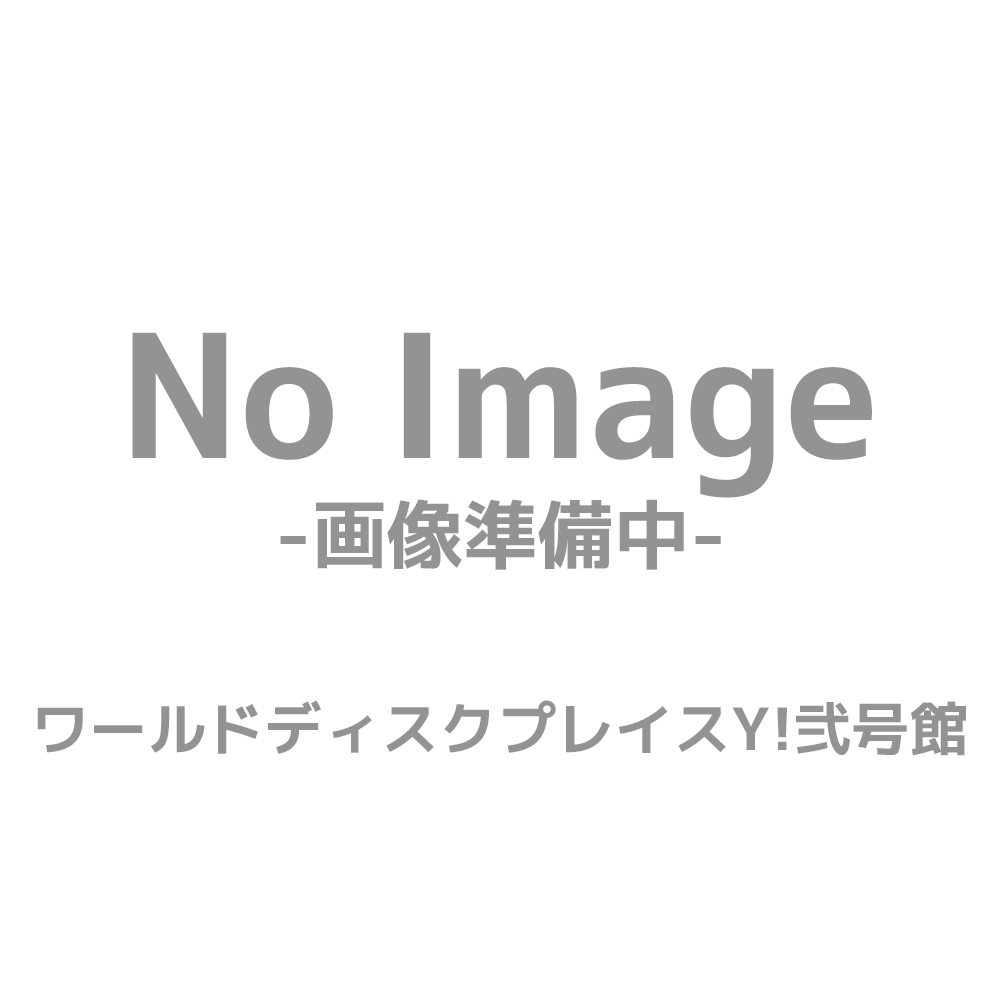Colibri合同会社についてですが、推定社員数は1~10人になります。所在地は中央区日本橋1丁目13-1-3Fになり、近くの駅は日本橋駅。株式会社航空総合研究所が近くにあります。また、法人番号については「5010003033207」になります。 Colibri合同会社の訪問時の会話キッカケ
Colibri合同会社に行くときに、お時間があれば「ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション」に立ち寄るのもいいかもしれません。
「
どうぞよろしくお願いします。
日本橋駅の近くで美味しい定食屋さんはありますか
ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションが近くにあるようですが、歩くと何分かかりますか
Colibri合同会社で働くの楽しそうですね
」
google map
東京メトロ・東西線の日本橋駅
東京メトロ・銀座線の日本橋駅
東京メトロ・半蔵門線の三越前駅
2023年02月09月 14時
【訪問介護の現場で働く方々の本音】事務所に通わなくてはならない理由とDX
2022年11月09月 11時
直行直帰が導入されているのは約7割!訪問介護に携わるヘルパーが求めるもの
2022年07月05月 11時
ますます加速する高齢化社会。
特に日本は2021年時点で高齢化率が28.9%となっており、超高齢化社会に突入していると言われています。
この高齢化社会においてニーズが高まっているのが、介護・福祉事業です。
介護・福祉事業にはさまざまなサービスが存在しますが、大きく分けると、介護を要する人が施設に通う通所型と、介護を要する人のところに介護者が訪問をして支援を行う訪問型があります。
特に訪問介護事業は、基本的に訪問先でサービスを提供する形式のため初期投資が少なくて済み、新規参入が増加しています。
では実際に訪問介護事業所を立ち上げる場合には、どのような点に注意が必要なのでしょうか。
また、採算の取れる事業所を運営するためには、どのようなポイントをおさえておくべきでしょう。
このような疑問点に答えるため、介護事業支援アプリColibri(https://colibri.jp/pages/product_videos)を手掛けるColibri合同会社は、訪問介護業の経営者を対象に、「訪問介護事業所立ち上げの実態」に関する調査を実施しました。
今回の調査に伴い、はじめに事業所を立ち上げてからの期間、事業所の人数規模、利用者数について伺いました。
▼今の事業所の立ち上げからの期間
1年未満:13.4%
1年以上~2年未満:18.2%
2年以上~3年未満:24.0%
3年以上~4年未満:12.6%
4年以上:31.8%
▼今の事業所の人員規模(複数箇所ある場合は合計)
5人未満:11.7%
5人以上10人未満:18.8%
10人以上20人未満:23.0%
20人以上30人未満:20.6%
30人以上40人未満:10.9%
40人以上50人未満:5.2%
50人以上:9.8%
▼利用者の人数(複数箇所ある場合は合計)
19人以下:17.4%
20人以上40人未満:21.9%
40人以上80人未満:21.6%
80人以上120人未満:18.1%
120人以上160人未満:9.2%
160人以上200人未満:3.5%
200人以上:8.3%
【人員の確保が大変...】訪問介護事業所立ち上げの苦労は?
ここからは実態について伺ってまいります。
まず事業所立ち上げの準備ではどういったことが大変だったのでしょうか。

「事業所立ち上げの準備で大変だったのはどんなことですか?(複数回答可)」と質問したところ、『人員の確保(46.1%)』と回答した方が最も多く、次いで『資金調達(45.8%)』『資格取得者の確保(44.7%)』と続きました。
人員の確保と回答された方が5割近くに上り最多となりました。
また、ほぼ並ぶ形で資金調達や資格取得者の確保が挙げられ、マンパワーが事業の根幹を支えるビジネスであることが窺えます。
続いて、準備の次の段階である事業所立ち上げの際にはどういった苦労があったか伺いました。
「実際に事業所を立ち上げるときに苦労したのはどんなことですか?(複数回答可)」と質問したところ、『人員がなかなか集まらなかった(53.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『思った以上に資金がかかった(42.3%)』『利用者がなかなか集まらなかった(35.0%)』となりました。
人員がなかなか集まらなかったという回答が半数以上に上り、準備段階と同様、人員の確保に苦労した方が最多となりました。
また、想定よりも初期投資の額が上振れしたという方も4割以上見られ、人と金の部分で苦労を強いられた方が多いことがわかりました。
事業所立ち上げ後に必要だと感じたシステムは?
事業所立ち上げ準備および立ち上げ段階で苦労したこととして、人員の確保と資金調達・想定以上の支出が挙げられました。
ここからは事業所立ち上げの際に導入したシステムについて伺ってまいります。

「事業所立ち上げと同時に導入したシステム(ソフト、アプリ、ツールなど)はありますか?(複数回答可)」と質問したところ、『シフト管理ツール(39.3%)』と回答した方が最も多く、次いで『給与計算ソフト(37.9%)』『勤怠管理システム(GPS等を利用し外出先で登録可能)(37.3%)』『計画書作成ツール(32.6%)』『電話(スマートフォン)(30.6%)』と続きました。
3割以上の方がシフト管理ツールを、またほぼ同数の方々が給与計算ソフトや、GPS等を利用し外出先で登録可能な勤怠管理システムを導入しているようです。
事業所立ち上げ際には必要性を感じずとも、業務が始まってくるこういったシステムも必要だったと、後々感じることもあるかと思います。実際にどのようなシステムの必要性を感じたのでしょうか。
「実際に事業所を立ち上げた後でどのようなシステム(ソフト、アプリ、ツールなど)が必要だと感じましたか?(複数回答可)」と質問したところ、『勤怠管理システム(GPS等を利用し外出先で登録可能)(38.1%)』と回答した方が最も多く、次いで『シフト管理ツール(36.6%)』『給与計算ソフト(33.0%)』『計画書作成ツール(30.8%)』『電話(スマートフォン)(24.4%)』と続きました。
なぜそのようなシステムの必要性を感じたのか理由を詳しく聞いてみました。
■システム利用で無駄なく効率化ができる!
・効率的に業務を回すために必要だった(20代/男性/東京都)
・人為的ミスが軽減できる(30代/男性/埼玉県)
・税理士経費削減(30代/男性/三重県)
・人件費削減(30代/女性/北海道)
・現場へ直行直帰のため、なかなかシフト管理が難しい(40代/男性/熊本県)
・円滑なサービス提供のため(60代/男性/東京都)
勤怠管理システムやシフト管理ツール、給与計算ソフト、計画書作成ツールといったシステムを導入することで、人為的ミスを防ぐことができたり、効率的に業務を回せたり、人件費削減ができるといった理由が挙げられました。
また、円滑なサービスの提供に繋がっているといった意見も見られました。
【ITシステムは必須!】ただし追加導入できている割合は…
先程の回答で、後々になって必要性を感じたシステムがあることについて分かりましたが、こういったシステムは実際に導入できているのでしょうか。

「事業所を立ち上げた後で必要だと感じたシステム(ソフト、アプリ、ツールなど)は、既に導入できていますか?」と質問したところ、『導入できている(65.2%)』『導入できていない(34.8%)』と、3割以上が導入できていないようです。
導入できていない理由について具体的に聞いてみました。
■導入したくてもできない現場の声
・資金面で厳しい(20代/男性/北海道)
・知識不足(30代/男性/愛知県)
・調査不足(30代/男性/愛知県)
・時間が足りてなく進めきれてない(30代/女性/沖縄県)
・すでにあるそれぞれのシステムとうまく連携ができないということがわかり、適応できるシステムベンダーが見つからなかったため(50代/男性/広島県)
・ヘルパーが新しい機器を使いこなせない (60代/女性/千葉県)
このような回答が寄せられました。
資金面での壁や知識不足が主に挙げられました。
システムを導入することで業務効率が上がり、円滑なサービスを行う助けになるメリットがあるものの、目先のことで精一杯でシステムを導入する余裕がない様子も見受けられました。
【まとめ】訪問介護事業所を立ち上げるなら、ITシステムは必須であるものの追いついていない事業所も
今回の調査で、訪問介護事業所立ち上げの際の実態について分かりました。
立ち上げ段階においては、人員がなかなか集まらなかったという回答に加え、資金が思った以上に必要だったという方も多数見られ、人・金の部分での苦労が大きかったようです。
立ち上げと同時に管理系のシステムを導入し業務効率化を図る動きも見られましたが、導入しきれていないところは後々になって必要性を感じたり、場合によっては必要性を感じているものの導入まで至っていないという事業所もあるようです。
昨今の時代に合わせた業務効率化や、他事業所の意見から見てみても、導入できない要因を解決し導入を進められる方法を模索してみてはいかがでしょうか。
訪問介護専用アプリなら『Colibri』

今回、「訪問介護事業所立ち上げの実態」に関する調査を実施したColibri合同会社(https://colibri.jp/)は、訪問介護専用アプリ『Colibri』(https://colibri.jp/pages/product_videos)を手掛けています。

・【勤怠給与計算から税金・保険控除まで一気通貫で!】Colibriと他社アプリ連携で事務作業を0に
Colibri上で直感的に管理される日々のシフトがそのまま給与計算や勤怠管理へ利用され、これらの集計や計算時間はほぼ0になります。また『ジョブカン』や『Money Forword』といった外部給与計算アプリとの連携により、税金・社会保険控除や給与支払いまでをシームレスに完結でき、事務作業に費やす時間を大幅に削減することが可能になります。
・【ヘルパーのアプリ】シンプル第一でヘルパー記録
ヘルパーさんが記録をする際に迷えないレイアウトを作りました。
サ責がColibriで訪問介護計画書を作成すれば、その内容が記録として自動表示され、ズレを未然に防ぎます。
自分のシフトはもちろん、訪問前に必要なサ責の指示や過去のヘルパーの記録が一目で確認できます。
利用者様の住所などもGoogleMapsでワンタッチで開けて便利です!
実績の確定は厚生労働省がテレワーク対策で推奨するGPSで行われ、その他QR等のタグは不要で追加コストは無く、ヘルパーさん達が既にお持ちのスマホでも利用できます。
・【サ責のアプリ】いつでもどこでもサ責の仕事が可能!

出先でも全てのシフト情報がリアルタイムで確認・編集できます。
自分のサービス、登録ヘルパーのシフト、そして同法人の他の事業所のシフト状況が一目で把握できます。
当然、ヘルパーアプリと同じように、サービス後の実施記録が作成できますし、事業所内掲示板で利用者様の情報を共有しつつ、それがそのまま記録化できます。
・【PCアプリ】サ責や管理者、経営者の組織管理を助ける最高のパートナー!

訪問事業の要であるシフトを全ての軸において設計されている「Colibri」は、ユーザーのシフト調整負担を毎日数時間単位で減らします。
付箋やメモ書きなどの代わりになる調整中リストや、複数事業所をまたいだシフト調整などシフト調整がICT化できない様々な可能性を排除しています。
集計された記録の中から、注意すべきポイントを「Colibri」が知らせるので、安心して利用者様や従業員のケアに時間を割いてください。
月末の面倒な給与計算も、基本給から手当まで自動化できる仕組みになっています。
・【シフト自動配列】
Colibriはスタッフの勤務時間、休み希望、過去のサービス履歴などを基にシフトの自動配列を可能にします。
しかし、各利用者に対する対応可能のスタッフを増やしたい、あるスタッフさんのサービス数を増やしたりスキルアップさせたい、このサービスだけはあの人にしか任せられないなど、サ責さんが色付けしたい箇所があることを知っています。
従って、サ責さんからシフト業務を奪うのではなく、サ責さんの最終シフトチェック前のお膳立てパートナーを目指しています。
■「Colibri」(コリブリ)の機能一覧
・記録アプリ
・シフト
・計画書
・給与計算
・情報共有
・勤怠管理
・勤務形態一覧表
・ソフト連携
■「Colibri」のサポートの考え方
Colibriは皆様の時間を大きく増やすことにこだわります。
サポートとは、アプリの使用方法についてのご質問に、ただ答えるだけではないと考えております。
導入時にできるだけ早く、確実に現場の皆様にColibriを使いこなして頂くために徹底的にサポートします。
Colibriの運用が安定した後も、さらなる効果を生み出すためにサポート、機能改善を行い続けます。
■資料請求はこちら:https://colibri.jp/contacts/new
■Colibri合同会社:https://colibri.jp/
■お問い合わせURL:https://colibri.jp/contacts/new
■お問い合わせTEL:03-6822-6895
調査概要:「訪問介護事業所立ち上げの実態」に関する調査
【調査期間】2023年1月10日(火)~2023年1月11日(水)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】1,002人
【調査対象】訪問介護業の経営者
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ
以前行った「コロナ禍の訪問介護」に関する調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000100118.html)では、「直行直帰制度(登録型ヘルパーとも)」の実態について明らかになりました。
直行直帰制度とは、介護スタッフが自宅から利用者の元へ直接訪問し、介護サービスや生活サポートを行った後に帰宅する制度のことです。
介護スタッフは事業所に立ち寄る必要がないため、時間や体力に余裕が生まれるばかりではなく、経費削減や介護サービスの向上、事業所の売上アップなども期待できます。
コロナ禍においては感染(クラスター)予防対策としても期待でき、訪問介護の働き方の1つとして、直行直帰制度は既に7割以上の事業所で導入されていることが分かりました。
しかし、事業所に立ち寄る必要がないのは良いですが、労働時間の透明化やサービス提供責任者(以後、サ責)とヘルパースタッフとの情報共有やコミュニケーションはどのようにしているのでしょうか?
また、直行直帰制度を訪問介護の現場に導入するためには、どのような課題があるのでしょう?
そこで今回、こうした現場の声を取り上げるために、訪問介護専用アプリ『Colibri』(https://colibri.jp/pages/product_videos)を手掛けるColibri合同会社(https://colibri.jp/)は、訪問介護従事者(現場職)を対象に、「コロナ禍での訪問介護における直行直帰」に関する調査を実施しました。
どれくらいが直行直帰できてる?現場職の実態とは
まずは、訪問介護事業者の直行直帰の実態について伺っていきたいと思います。

「直行直帰できていると思いますか?」と質問したところ、4割近い方が『いいえ(39.2%)』と回答しました。
前述の通り、以前実施した調査では直行直帰制度を取り入れている事業所が7割以上にのぼることが明らかになりましたが、実現できていない現場職の方も多いようです。
では、1日一件以上稼働する日は週に何日あるのでしょうか?
「平均的に週何日勤務されますか?(1日一件以上稼働する日)」と質問したところ、『毎日(45.8%)』と回答した方が最も多く、次いで『週に3~4回(33.1%)』となりました。
【最も多いのは記録提出!】直行直帰できない理由とは
先程の調査の結果、4割近い方が直行直帰できていない実態が浮き彫りになりました。
では、実際に事務所に出勤するのは週に何回あるのでしょうか?

そこで、「平均的に事務所に行く回数は何回ですか?」と質問したところ、『毎日(38.6%)』と回答した方が最も多く、次いで『週に1~2回(27.5%)』『週に3~4回(26.9%)』となりました。
毎日と回答した方が4割近くいますが、週に3~4回と回答した方を合わせると、6割以上の方が週に3~4回以上事務所に出勤しているようです。
直行直帰ができない理由としては、「事務所に行かないとできない用事がある」ことが大きな理由かと思いますが、事務所に行く理由とは何なのでしょうか?
続いて、「事務所に行く理由は何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『記録提出(57.3%)』と回答した方が最も多く、次いで『シフト確認(48.4%)』『出退勤(47.0%)』となりました。
最も多いのが記録提出となり、その日の業務を報告するためにやむを得ず出勤している方が多いようです。
一方で、シフト確認や出退勤など、わざわざ通わなくてもできそうな業務が理由で直行直帰できていない方もいることが分かりました。
では、実際にどんな理由で出社しているのか、具体的な理由を聞いてみました。
■ どんな理由で事務所に通っている?
・月末、中間の際の会議出席のため(20代/女性/東京都)
・シフトの確認や、管理者への報告など(40代/女性/栃木県)
・記録提出に行くのがほぼ毎日、月末月初に会議、打ち合わせに行きます(40代/女性/愛知県)
・報告書だけでは伝わらない事もあるので直接会って話すため(40代/男性/大阪府)
などの回答が得られました。
様々な理由があるようですが、会議やシフトの確認、報告書提出などが多く挙げられました。
完全に出社しない形は取れていないようで、定期的な出社を必要としている方が多いようです。
どんなシステムを取り入れればオンラインに変更できる?
4割近い方が直行直帰できず、毎日事務所へ通っていることが分かりました。
その中でもシフト確認や出退勤といった、工夫を行えばわざわざ事務所へと通わなくても済みそうな業務もありますが、どのようなソフトやアプリがあればオンラインに変更できるのでしょうか?

そこで、「事務所出社理由はどのようなソフト、アプリがあればオンラインに変更可能ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『勤怠管理システム(GPS等を利用し外出先で登録可能)(44.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『シフト管理ツール(42.3%)』『計画書作成ツール(27.5%)』と続きました。
最も求められているのは、勤怠管理システムのようです。
GPSを使用することで、実際に現場で業務にあたっていることも証明できるでしょう。
また、シフト管理ツールや計画書作成ツールなど、今まで書面で提出していたものをデジタル化することで、オンライン対応が叶い、直行直帰への道が開かれると感じているようです。
【現在導入しているのは電話が3割以上!】システム導入で楽になった業務とは
勤怠管理システムやシフト管理ツール、計画書作成ツールなどがあれば、直行直帰が叶うと感じている方が多いことが分かりました。
では、現在使っているツールにはどのようなものがあるのでしょうか?

「現在導入しているシステムやソフト、ツールは何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『電話(スマートフォン)(31.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『メール(26.7%)』『シフト管理ツール(25.7%)』と続きました。
スマートフォンやメールといった一般的に利用されているようなツールが上位を占めていますが、シフト管理ツールも2割以上が取り入れていることが分かります。
では、そういったシステムやツールの導入によりどのような部分が楽になったのでしょうか?
「前の説問で選択したシステムを導入又は利用していて楽になった業務は何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『オンライン会議などにより情報共有や収集が可能になった(24.3%)』と回答した方が最も多く、次いで『記録がどこでも書けるようになった(22.3%)』『出退勤を事業所で行う必要がなくなり、直行直帰できるようになった(20.6%)』となりました。
オンライン会議や介護記録システムなどを取り入れることで、情報を共有しやすくなったと感じているようです。
また、実際にツールを取り入れたことで、直行直帰ができるようになった方も2割にのぼり、システムのデジタル化は直行直帰の実現において非常に重要な役割を担っていることが分かります。
現場で働く方々が感じる従来の勤務形態に対する本音
様々なオンラインシステムやソフトの導入により、直行直帰が実現できている方が2割以上いることが分かりました。
では、従来の方法で介護サービスを続けていくことに対して、どのような不安や不満があるのでしょうか?

「ソフトの利用有無に関わらず、従来の方法で訪問介護サービスを続けることに対して具体的に不安や不満はありますか?(複数回答可)」と質問したところ、『勤怠管理を事業所で行うのは時間がもったいない(外出先で出退勤できたら嬉しい)(35.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『紙面記録の管理や提出が面倒(33.1%)』『研修や会議をオンラインできる仕組みにしてほしい(32.6%)』と続きました。
勤怠管理の手間や紙面記録の提出に関する手間に、不満を感じている方が多いようです。
また、コロナ禍でスタンダードになってきた、研修や会議のオンライン化を今後も活用してほしいと感じている方もいることが分かりました。
では、これらの不満や改善点を解決するためには、どんなソフトやアプリが必要なのでしょうか?
「前の説問で感じた不満や改善点を解決できそうなソフトやアプリは何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『勤怠管理システム(GPS等を利用し外出先で登録可能)(27.2%)』と回答した方が最も多く、次いで『シフト管理ツール(25.8%)』『介護記録システム(24.1%)』となりました。
勤怠管理やシフト管理、介護記録が行えるシステムツールが上位を占めており、現在の不満を解消するためには、デジタルの活用が必要不可欠となっています。
様々なシステムツールを導入することこそが、訪問介護業界での直行直帰を実現する鍵となりそうです。
訪問介護の現場でシステムツールを利用すれば直行直帰は夢じゃない!
コロナ禍での訪問介護における直行直帰の実態を調べてみると、4割近い方が毎日事務所へと通っていることが分かり、実現できていない様子が窺えます。
事務所へ通う理由は、記録提出やシフト確認、出退勤などが挙げられ、そのためだけに出社しなくてはならないことに不満を感じている方も多いようです。
そういった不満を解消するためには、GPSを使用した勤怠管理システムやシフト管理ツール、介護記録システムなどの導入を希望される方が多く、無駄を減らすためのオンラインの活用が鍵となっています。
システムツールを導入し、情報共有がしやすい環境に整えていくことが、直行直帰への近道になりそうです。
訪問介護専用アプリなら『Colibri』

今回、「コロナ禍での訪問介護における直行直帰」に関する調査を実施したColibri合同会社(https://colibri.jp/)は、訪問介護専用アプリ『Colibri』(https://colibri.jp/pages/product_videos)を手掛けています。
・【ヘルパーのアプリ】シンプル第一でヘルパー記録
ヘルパーさんが記録をする際に迷えないレイアウトを作りました。
サ責がColibriで訪問介護計画書を作成すれば、その内容が記録として自動表示され、ズレを未然に防ぎます。
自分のシフトはもちろん、訪問前に必要なサ責の指示や過去のヘルパーの記録が一目で確認できます。
利用者様の住所などもGoogleMapsでワンタッチで開けて便利です!
実績の確定は厚生労働省がテレワーク対策で推奨するGPSで行われ、その他QR等のタグは不要で追加コストは無く、ヘルパーさん達が既にお持ちのスマホでも利用できます。
・【サ責のアプリ】いつでもどこでもサ責の仕事が可能!
出先でも全てのシフト情報がリアルタイムで確認・編集できます。
自分のサービス、登録ヘルパーのシフト、そして同法人の他の事業所のシフト状況が一目で把握できます。
当然、ヘルパーアプリと同じように、サービス後の実施記録が作成できますし、事業所内掲示板で利用者様の情報を共有しつつ、それがそのまま記録化できます。
・【PCアプリ】サ責や管理者、経営者の組織管理を助ける最高のパートナー!
訪問事業の要であるシフトを全ての軸において設計されている「Colibri」は、ユーザーのシフト調整負担を毎日数時間単位で減らします。
付箋やメモ書きなどの代わりになる調整中リストや、複数事業所をまたいだシフト調整などシフト調整がICT化できない様々な可能性を排除しています。
集計された記録の中から、注意すべきポイントを「Colibri」が知らせるので、安心して利用者様や従業員のケアに時間を割いてください。
月末の面倒な給与計算も、基本給から手当まで自動化できる仕組みになっています。
・【シフト自動配列】
Colibriはスタッフの勤務時間、休み希望、過去のサービス履歴などを基にシフトの自動配列を可能にします。
しかし、各利用者に対する対応可能のスタッフを増やしたい、あるスタッフさんのサービス数を増やしたりスキルアップさせたい、このサービスだけはあの人にしか任せられないなど、サ責さんが色付けしたい箇所があることを知っています。
従って、サ責さんからシフト業務を奪うのではなく、サ責さんの最終シフトチェック前のお膳立てパートナーを目指しています。
■「Colibri」(コリブリ)の機能一覧
・記録アプリ
・シフト
・計画書
・給与計算
・情報共有
・勤怠管理
・勤務形態一覧表
・ソフト連携
■「Colibri」のサポートの考え方
Colibriは皆様の時間を大きく増やすことにこだわります。
サポートとは、アプリの使用方法についてのご質問に、ただ答えるだけではないと考えております。
導入時にできるだけ早く、確実に現場の皆様にColibriを使いこなして頂くために徹底的にサポートします。
Colibriの運用が安定した後も、さらなる効果を生み出すためにサポート、機能改善を行い続けます。
■資料請求はこちら:https://colibri.jp/contacts/new
■Colibri合同会社:https://colibri.jp/
■お問い合わせURL:https://colibri.jp/contacts/new
■お問い合わせTEL:03-6822-6895
調査概要:「コロナ禍での訪問介護における直行直帰」に関する調査
【調査期間】2022年10月6日(木)~2022年10月7日(金)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】1,005人
【調査対象】訪問介護従事者(現場職)
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ
高齢化率が上昇し続ける中、注目されているのが在宅介護支援です。
慣れ親しんだ家で老後を安心して過ごしたい、と願う高齢者の数は多く、在宅介護サービスの需要が高まってきています。
在宅介護サービスの中心になるのは、ホームヘルパーなど現場で働く人たちです。
厚生労働省の資料によると、ホームヘルパーとして働く方の8割以上が女性で、その6割以上はパート勤務となっています。
こうしたホームヘルパーなど現場職の方たちは、高齢者のお世話をするだけでなく、限られた時間の中で事業所への報告などの業務も行わなくてはなりません。
また、コロナ禍においては、自身や家族がコロナ陽性あるいは濃厚接触者となったため仕事に出られない、介護をされる高齢者の方の体調が悪化してしまったなど、多くの不具合も生じているようです。
では実際、現場で働いている方たちはコロナ禍での訪問介護にどのような変化や悩みを持っているのでしょうか?
そこで今回、こうした現場の声を取り上げるために、訪問介護専用アプリ『Colibri』(https://colibri.jp/pages/product_videos)を手掛けるColibri合同会社(https://colibri.jp/)は、訪問介護に従事している方(現場職)を対象に、「コロナ禍の訪問介護」に関する調査を実施しました。
※本調査は、弊社ソフトユーザーではなく、条件に該当する無作為に抽出した方を対象に調査を実施しております。
【直行直帰を行っていた事業所は7割以上】なぜ直行直帰できないのか?
まずは、2020年当時の直行直帰に関する実態を調査していきたいと思います。

「2020年当時、直行直帰は行っていましたか?(※2020年1月〜12月まで)」と質問したところ、2割以上の方が『いいえ(25.5%)』と回答しました。
直行直帰を取り入れている方が多い中で、まだ約2割の方が導入していなかったことが分かります。
では、一体なぜ直行直帰を行っていなかったのでしょうか?
ここからは、2020年当時直行直帰を行っていなかった方に伺っていきたいと思います。
「直行直帰ができていなかった理由を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『事務所で出社退社の記録をする必要があった(51.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『仕事に必要な用具や車両などを事務所に取りに行く、または戻す必要があった(39.0%)』『報告書を事務所に提出する必要があった(27.4%)』と続きました。
どのタイミングで出社している?ヘルパーが出社を求められる理由とは
先程の調査により、2割以上の方が2020年当時直行直帰を取り入れていなかったことが分かりましが、では、どのタイミングで出社をしていたのでしょうか?

「出社する必要があったタイミングを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『訪問業務開始前(61.0%)』『訪問業務終了後(54.8%)』『業務と業務の間(34.8%)』という回答結果になりました。
業務開始前が最も多くなりましたが、業務後に出社が必要な方や、作業の間に出社を余儀なくされていた方もいること(少なくないこと)が分かりました。
では、出社する際、事業所にはどれくらいスタッフが在籍していたのでしょうか?
そこで、「出社した際、事業所には何人くらいのスタッフがいることが多かったですか?」と質問したところ、『0人(3.8%)』『1、2人(25.9%)』『3〜5人(33.2%)』『6〜10人(23.6%)』『11人以上(13.5%)』という回答結果になりました。
事業所に勤務する人数によるかもしれませんが、3〜5人が最も多いようです。反対に0人が最少となり、事業所には誰かしらスタッフが在籍していることが窺えます。
では、出社しないとできない業務とは一体何なのでしょうか?

続いて、「出社しないとできなかった業務を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『記録の共有(51.4%)』と回答した方が最も多く、次いで『勤務時間の管理(42.9%)』『引き継ぎ(40.2%)』と続きました。
訪問介護に関する記録の共有が半数以上となり、いち早く情報をシェアするために出社しているようです。
また、勤務時間の管理や引き継ぎなども出社しないとできない業務であることが分かりました。
【6割以上が直行直帰を望んでいる】本当に出社は必要?
先程の調査の結果、2020年当時直行直帰を行っていなかった2割以上の方は、記録の共有や勤務時間の管理のために出社していた方が多いことが分かりました。
では、実際に直行直帰を望んでいる方はどれくらいいるのでしょうか?
ここからは、訪問介護に従事しているみなさんに伺っていきたいと思います。

そこで、「直行直帰と出社、選べるとしたらどちらがいいですか?」と質問したところ、6割以上の方が『直行直帰(68.2%)』と回答しました。
非常に高い割合で、直行直帰を望んでいることが分かります。
その理由について詳しく伺っていきましょう。
■直行直帰が良い理由とは
・事務所に立ち寄るのが手間(20代/女性/東京都)
・接する人の人数を減らしたいから(30代/男性/和歌山県)
・出退勤の時間短縮と融通がきくため(30代/男性/千葉県)
・出社すると遠回りになるので(40代/男性/北海道)
などの回答が得られました。
事業所に戻ることで遠回りになってしまうため手間を省きたいなど、出退勤の時間短縮を望んでいる方が多いことが分かりました。
また、コロナ禍ということもあり、できるだけ人との接触を減らす工夫として直行直帰を望んでいる方もいるようです。
では、現在直行直帰はどれくらい導入されているのでしょうか?
「現在、直行直帰は導入されていますか?」と質問したところ、約7割の方が『導入されている(69.2%)』と回答しました。
7割という数字は多いように感じますが、直行直帰ができていない方もいるのが現状のようです。
直行直帰を求めている方も多いことから、オンラインなどを活用し、必要な時だけ出社するような体制を作る必要があるのかもしれません。
【コロナ対策が大変】コロナ禍での介護の実態
最後に、コロナ禍での介護の実態について伺っていきたいと思います。

「コロナ禍になって、担当していた利用者様の人数に増減はありましたか?」と質問したところ、『大きく減少した(9.4%)』『やや減少した(36.2%)』『変わらない(44.2%)』『やや増加した(8.6%)』『大きく増加した(1.6%)』という回答結果になりました。
「変わらない」という回答が最も多く、「やや減少した」が続いています。
人との距離が近い業務だからこそ心配に感じる方もいるようですが、ご時世関係なく必要とされる仕事であるため、そこまで大きな増減はなさそうです。
では、コロナ禍での訪問介護で、困っていることや難しいと感じていることなどはあるのでしょうか?
詳しく聞いてみました。
■コロナ禍での訪問介護で困っていることとは
・感染対策が難しい(20代/女性/青森県)
・一人当たりの担当人数が多い(20代/女性/東京都)
・マスクをしてもらうことができないことと接触もさけられないこと(40代/男性/北海道)
・同居ご家族の同意(50代/男性/奈良県)
などの回答が得られました。
近い距離で対応するため感染の危険性が高い環境であることから、感染対策への難しさを感じているようです。
日々の業務の他に、十分な意識を持った
Colibri合同会社の情報
東京都中央区日本橋1丁目13-1-3F
法人名フリガナ
コリブリ
住所
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13-1-3F
推定社員数
1~10人
周辺のお天気
周辺の駅
4駅都営・都営浅草線の日本橋駅
地域の企業
地域の観光施設
法人番号
5010003033207
法人処理区分
新規
プレスリリース
【訪問介護事業所立ち上げの実態】事業立ち上げ後、3割以上は必要と感じたシ
【訪問介護事業所立ち上げの実態】事業立ち上げ後、3割以上は必要と感じたシステムを導入できていないと回答。事業拡大のために必要なシステム導入の実状は?
2023年02月09月 14時
後々必要だと感じたシステムとは!?Colibri合同会社(本社所在地:東京都中央区、代表社員:鎌原 欣司)は、訪問介護業の経営者を対象に、「訪問介護事業所立ち上げの実態」に関する調査を実施しました。
【訪問介護の現場で働く方々の本音】事務所に通わなくてはならない理由とDX化の実態とは
2022年11月09月 11時
3割以上が勤怠管理を事業所で行うのは時間がもったいないと回答Colibri合同会社(本社所在地:東京都中央区、代表社員:鎌原 欣司)は、訪問介護従事者(現場職)を対象に、「コロナ禍での訪問介護における直行直帰」に関する調査に関する調査を実施しました。
直行直帰が導入されているのは約7割!訪問介護に携わるヘルパーが求めるものとは?
2022年07月05月 11時
半数以上の方が情報の共有で出社していたことが判明Colibri合同会社(本社所在地:東京都中央区、代表社員:鎌原 欣司)は、訪問介護に従事している方(現場職)を対象に、「コロナ禍の訪問介護」に関する調査を実施しました。